| 参考リンク |
|
 構 成 構 成 |
|
|
|
|
|
|
|
設備方式による分類、放出方式による分類は 不活性ガス消火設備をご参照ください。 |
|
|
|
圧力方式には 加圧式 と 蓄圧式 があり、消火薬剤の種別に関係なくどちらの方式も使用できます。 |
|
|
|
|
 蓄圧式 蓄圧式
|
|
|
蓄圧式はほぼ不活性ガス(二酸化炭素消火設)に準じる構成ですが、排出装置やクリーニング装置 |
|
|
が付加されています。 |
|
|
|
| 令-消防法施行令 |
|
 加圧式 加圧式 |
| 則-同 施工規則 |
|
|
| 法-消防法 |
|
 全域放出方式 全域放出方式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
起動装置、制御装置、音響警報装置、起動用ガス容器、加圧用ガス容器、圧力調整装置、貯蔵タ |
|
|
ンク、ガス導入弁、放出弁、定圧作動装置、排出装置、クリーニング装置選択弁、配管、噴射ヘッド |
|
|
火災感知装置、非常電源等から構成されています。 |
|
|
|
|
|
 局所放出方式 局所放出方式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
放出表示灯を必要としない以外はほぼ全域放出方式と同じ構成です。 |
|
|
|
|
|
 移動式 移動式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
格納箱にユニット一式を収納するタイプが一般的で、加圧用ガスには二酸化炭素を用いますが、 |
|
|
窒素ガスを使用する場合は圧力調整装置が必要です。 |
|
|
屋上の駐車場などに設置されているものです。 |
|
|
|
|
|
 消 火 剤 消 火 剤 |
|
|
|
|
|
粉末消火薬剤は人体に対して毒性の無いものを使用しています。主として炭酸水素ナトリュウム等の |
|
|
アルカリ金属塩を主成分とするものと、燐酸塩類を主成分とする酸性のものがあります。 |
|
|
大変微細な粉末(単位で表すと180マイクロメートル以下)でシリコン樹脂等で防湿加工を施しています。 |
|
|
消火薬剤には次の表のような種類があります。 |
|
|
|
|
|
| 消火薬剤の種別 |
主成分 |
適応火災 |
| 第一種粉末 |
炭酸水素ナトリウム |
B.C |
| 第二種粉末 |
炭酸水素カリウム |
B.C |
| 第三種粉末 |
リン酸塩類 |
A.B.C |
| 第四種粉末 |
炭酸水素ナトリウムと尿素との反応物 |
B.C |
|
|
|
|
|
|
上記の表にはありませんが、危険物の内第一類のアルカリ金属の過酸化物、第二類の鉄粉、金属 |
|
|
粉、マグネシウム類、第三類の内禁水生物品を対象とした第五種粉末もあります。 |
|
|
|
|
|
 配 管 配 管 |
|
|
|
|
|
配管は専用で、鋼管を使う場合はJIS G 3452と同等若しくは以上のもので、蓄圧式のものの内、 |
|
|
圧力が2.5MPa以上4.2Mpa以下のものにあっては、JIS G 3454のスケジュール40と同等若しくは |
|
|
以上のものを使わなければいけません。 |
|
|
そのほか管継ぎ手についてもフランジ、ねじ込み・差込継ぎ手等JIS規格で使用材料が決められ |
|
|
ています。 |
|
|
配管は大変複雑で、加圧・混和のための配管・放出のための配管・残圧排出のための配管・残 |
|
|
圧排出のための配管クリーニングのための配管等、全てが必要です。 |
|
|
|
|
|
 消火剤貯蔵容器 消火剤貯蔵容器 |
|
|
|
|
|
薬剤の貯蔵容器への充填比は次の通りです。 |
|
|
|
|
|
| 消火薬剤の種別 |
充填比の範囲 |
| 第一種粉末 |
0.85-1.45 |
| 第二種又は第三種粉末 |
1.05-1.75 |
| 第四種粉末 |
1.50-2.50 |
|
|
|
|
|
|
貯蔵容器等にはその区分に応じて、「二酸化炭素消火設備の容器弁、安全装置及び破壊板の |
|
|
基準」に基づく安全装置又は容器弁を設けるとともに、見やすい場所に充填消火薬剤量、消火 |
|
|
剤の種類、製造年月、製造者名の他に加圧式の貯蔵タンクを用いる場合は、最高使用圧力を |
|
|
明示しなければなりません。 |
|
|
|
|
|
 定圧作動装置 定圧作動装置 |
|
|
|
|
|
定圧作動装置は加圧式の貯蔵タンクに設けられるもので、告示に定められた基準に適合する |
|
|
物を設置しなければなりません。 |
|
|
|
|
|
 定圧作動装置は貯蔵タンクごとに設けなければならない。 定圧作動装置は貯蔵タンクごとに設けなければならない。 |
|
|
 起動装置の作動後貯蔵タンクの内圧が設定圧力に達したとき放出弁を自動的に開放さ 起動装置の作動後貯蔵タンクの内圧が設定圧力に達したとき放出弁を自動的に開放さ |
|
|
せる仕組みでなければならない。 |
|
|
|
|
|
参考 定圧作動装置の基準 告示四号 ⇒ |
|
|
|
|
|
 クリーニング機構 クリーニング機構 |
|
|
|
|
|
貯蔵容器には残留ガスを排出するための排出装置、配管には残留消火薬剤を処理するための |
|
|
クリーニング装置を設けなければいけません。 |
|
|
|
|
|
 加圧用ガス容器 加圧用ガス容器 |
|
|
|
|
|
加圧用又は蓄圧用ガスは二酸化炭素とし、次の表に基づき算出します。
|
|
|
|
|
|
ガスの
種別 |
加圧用ガス |
蓄圧用ガス |
| 窒素ガス |
消化剤1Kg当たり40ℓ以上でクリーニングに必要な量も含む |
消火薬剤1Kg当たり10ℓにクリーニングに必要な量を加えた量以上 |
| 二酸化炭素 |
消火薬剤1Kg当たり20gにクリーニングに必要な量を加えた量以上 |
消火薬剤1Kg当たり20gにクリーニングに必要な量を加えた量以上 |
|
|
|
|
|
|
クリーニング用ガス量 |
|
|
|
|
|
ガスの
種別 |
加圧式 |
蓄圧式 |
| 窒素ガス |
- |
10ℓ/Kg |
| 二酸化炭素 |
20g/Kg |
|
|
|
|
|
|
 設置基準 設置基準 |
|
|
|
|
|
 放出方式の限定 放出方式の限定 |
|
|
|
|
|
|
道路の用に供される部分は、全域放出方式又は局所放出方式を設けてはならず屋上部分に限り |
|
|
移動式が認められています。 |
|
|
|
|
|
 消火薬材量 消火薬材量 |
|
|
|
|
|
|
防火対象物の区分の別はありませんので、全域放出・局所放出方式とも消火剤の種別ごとに定 |
|
|
める単位消火薬剤量の数値を用いて計算します。 |
|
|
|
|
|
| 自動閉鎖装置有り |
自動閉鎖装置無し |
| 0.60Kg |
4.5Kg |
| 0.36Kg |
2.7Kg |
| 0.36Kg |
2.7Kg |
| 0.24Kg |
1.8Kg |
|
|
|
|
|
|
局所放出方式の消火薬剤量 |
|
|
|
|
|
| 防護対象物 |
消火剤の量 |
| 可燃性固体類又は可燃性液体類を上面を開放した容器に貯蔵する場合その他火災のときの燃焼面が一面に限定され、かつ、可燃物が飛散するおそれがない場合 |
| 消火薬剤の種別 |
表面積1㎡当たりの薬剤量 |
| 第一種粉末 |
8.8Kg |
| 第二種粉末 |
5.2Kg |
| 第三種粉末 |
5.2Kg |
| 第四種粉末 |
3.6Kg |
|
| 上記以外の場合 |
次の式によって求められた量に防護空間の体積Vを乗じた量
Q=X-Ya/A
Q: 単位体積あたりの消火剤の量 Kg/㎥
a : 防護対象物の周囲にある壁の総面積 ㎡
A : 防護空間の壁の面積の合計 ㎡
X及びYの値
| 消火薬剤の種別 |
Xの値 |
Yの値 |
| 第一種粉末 |
5.2 |
3.9 |
| 第二種粉末 |
4.4 |
3.3 |
| 第三種粉末 |
4.0 |
3.0 |
| 第四種粉末 |
2.0 |
1.5
|
|
|
|
|
|
|
|
 移動式 移動式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ノズルは告示基準に適合するもので、放射量は毎分次の表に定められた量以上を放出できるも |
|
|
のである事が定められています。貯蔵量はノズル一つに対して次の量以上の量を貯蔵するよう |
|
|
規定されています。 |
|
|
|
|
|
放射量及び薬剤貯蔵量 |
|
|
|
|
|
| 消火薬剤の種別 |
消火剤量 |
薬剤貯蔵量 |
| 第一種粉末 |
45Kg |
50Kg |
| 第二種粉末 |
27Kg |
30Kg |
| 第三種粉末 |
27Kg |
30Kg |
| 第四種粉末 |
18Kg |
20Kg |
|
|
|
|
|
|
移動式第3種粉末 |
|
|
|
|
|
| 移動式3種粉末消火設備 |
 |
|
|
|
|
 平成28年2月移動式粉末消火設備等の点検基準が改正されています。 平成28年2月移動式粉末消火設備等の点検基準が改正されています。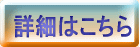 |
|
|
|
|
|
 配管上の制約 配管上の制約 |
|
|
|
|
|
粉末消火設備では如何にして貯蔵容器から噴射ヘッドまで消火剤と放出ガスを適切な圧力と
|
|
|
量を併せて流すかが重大な要点です。ですからこれらを満足させるため配管を分岐する場合は、 |
|
|
トーナメント形式による配管と、それに伴う継ぎ手相互の距離として、管径の20倍以上を確保す |
|
|
るという制約があります。 |
|
|
|
|
|
詳しくは 施行規則第21条の4 |
|
|
消火設備の対応表はこちら |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
消防用設備の設置単位は基本的には 棟 単位なのですが、令8区画や収容人員の算定複合用途に係わる算定 |
|
|
床面積の算定等によりその設置基準は大きく変化しますので、ご注意ください。 |
|
|
|
|
|
こちらの 消防用設備の算定資料 もご参照下さい。 令別表第一PDFはこちら |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 株式会社 西日本防災システム |
|
|
|
 |